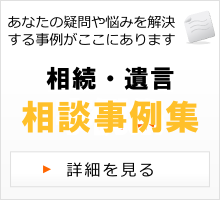遺言による遺贈に関する基礎知識
(1) 遺贈とは
遺贈とは、遺言によって遺産の全部又は一部を特定の人に無償で与える行為、いわゆる贈与することをいいます。
遺贈を受ける者を「受遺者」といい、遺贈を実行すべき義務を負う者を「遺贈義務者」といいます。
死因贈与は死亡を原因として行われる贈与で、遺贈とよく似ていますが、死因贈与は契約であり、遺贈は遺言者が単独で行う法律行為です。
(a)受遺者
受遺者は相続人、その他の第三者のみならず、会社などの法人もなれます。胎児も受遺者となることができます。
相続欠格者は、受遺者となることができません。
受遺者は、遺言の効力が発生した時に生存している必要があり (同時存在 の原則)、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには遺贈の効力が生じません。
(b)遺贈義務者
遺贈義務者は原則として相続人ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺贈義務者となります。
(2) 遺贈の無効・取消
(a)遺贈の無効
遺言は被相続人の最終意思を明らかにする単独の法律行為ですので、遺言による贈与ということもでき、一般の意思表示ないし法律行為の無効または取消に関する規定が準用されています。
それ以外にも遺贈特有の無効原因として次のような事があります。
ア)遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合。
イ)停止条件付遺贈において、その条件の成就前に受遺者が死亡した場合。
ウ)遺贈の目的たる権利が遺言者死亡の時に相続財産に属していない場合。
遺贈が効力を生じないとき、又は遺贈の放棄によってその効力がなくなったときには、受遺者が受けるべきであった相続財産は、相続人に帰属しますが、遺言によって別段の定めをすることがで、その定めがあればそれに従います。
(b)遺贈の取消
負担付遺贈について、受遺者が負担した義務を履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときには、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
取消が認められた場合には、受遺者が受けるべきであった権利は、遺言に別段の定めがない限り相続人に帰属します。
(3) 遺贈の承認と放棄
遺贈は遺言者の単独行為であり、遺言者の死亡の時に効力を生ずるものとされていますが、受遺者は遺贈を受ける事を強制されるわけではなく、受遺者側で、遺贈を承認するか放棄するかの判断をする自由があります。
ただし、受遺者が長期間にわたって放棄も承認もせずにいると、遺贈義務者(相続人等)の地位は不安定になります。そこで、受遺者が承認または放棄をしないときには、遺贈義務者その他の利害関係人は相当の期間を定めて、期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨を受遺者に催告することができます。期間内に受遺者が回答をしないときには、受遺者は遺贈を承認したものとみなされます。
一度なされた遺贈の承認または放棄は、原則撤回はできません。遺贈が放棄されたときは、遺言に別段の定めがない限り、受遺者が受けるべきであった相続財産は遺言者の相続人に帰属します。
(4) 包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈とは、 「遺産の何分の一を甲に、何分の一を乙に与える」 というように、遺産の全部またはその割合を定めて行う遺贈であり、特に目的物を特定しないでする遺贈をいいます。
特定遺贈とは、例えば 「自宅の土地建物を甲に与える」 というように、特定された具体的な財産を対象とする遺贈をいいます。
両者の主たる相違は、包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有するとされていて、積極、消極両財産を承継するのに対し、特定遺贈は積極財産だけを承継する点にあります。
(a)包括遺贈の効力
包括遺贈による包括受遺者は、相続人ではありませんが相続人と同一の権 利義務を有すると規定されています。
したがって、包括受遺者は、遺言者の一身専属権を除き、すべての財産上の権利義務を遺贈を受けた割合で承継し、ほかに相続人または包括受遺者がいるときには、これらの者と共同相続したのと同一の権利義務関係をが生じます。遺産共有状態は遺産分割によって解消することになります。
しかし、包括受遺者は法定の相続人そのものではないため、以下のような差異もあります。
ア)法人と包括遺贈
法人は包括受遺者にはなれますが、相続人にはなれません。
イ)遺留分及び代襲相続権
一定の相続人には、遺留分権や代襲相続権が認められていますが、包括受遺者には、遺留分権や代襲相続権は認められておりません。
(b)特定遺贈の効力
相続財産に属する特定物または特定の債権が遺贈の目的とされている場合、遺言の効力が発生したときに、その権利が受遺者に移転します(大審院判昭15.2.13等)。