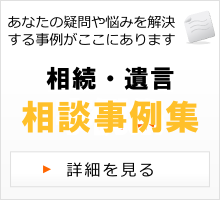遺留分の基礎知識
1.遺留分
(1) 遺留分について
1. 遺留分
被相続人には、生前の財産処分の自由のほかに遺言をすることができ、死後においても自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分で決めることができます。
しかし、一定の法定相続人については、決まった割合で被相続人の財産を承継する権利が保障されています。これを遺留分といいます。
自己の遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、遺留分における割合で財産の返還を求めることができます。
この権利を遺留分減殺請求権といいます。
(2) 相続発生前に遺留分権
1. 遺留分権利者の地位
被相続人の死後、遺留分権利者は、被相続人の遺産や生前贈与された財産に対して一定割合での減殺請求をすることができますが、被相続人の生前に、遺留分を根拠とした法的請求ができるかどうかが問題となる場合があります。
将来の遺留分権利者となることができる人でも、相続放棄、相続の欠格、廃除等によってその地位を喪失する可能性があります。また現在の財産額では遺留分を侵害していても、相続開始時には財産がもっと増加しており、遺留分の侵害が生じない場合も考えられます。つまり、遺留分の侵害が生じるかどうかは相続発生時まで確定できないため、相続発生以前に遺留分を基にした請求は認められません。
(3) 遺留分権利者の範囲
1. 遺留分権利者
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。
すなわち、配偶者、子(あるいは子の代襲相続人)、直系尊属に遺留分権が認められています。
2. 包括受遺者
遺言で一定割合または全部の財産を遺贈された第三者のことを包括受遺者といいますが、包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されているため、遺留分権を有するかどうかが問題となります。遺留分権は相続人に対する権利であるため、包括受遺者には遺留分権は認められておりません。
3. 相続権を喪失した場合
遺留分の制度趣旨としては、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化、あるいは、遺留分権利者の生活保障が考えられており、これは相続資格と連動するものといいえます。
よって、相続資格の喪失は遺留分権利者の地位も喪失することになります。
相続欠格者、相続人から廃除された者、相続放棄をした者には遺留分は認められません。
但し、相続の欠格、廃除の場合には代襲相続が開始しますので、その直系卑属に遺留分が認められます。
(4) 遺留分の放棄
1. 遺留分の放棄
遺留分は、遺留分権利者のために、被相続人の生前贈与や遺言の自由を制約するという制度ですから、遺留分権利者において、その権利を放棄する自由が認められております。
つまり、遺留分を被相続人の生前に、あるいは死後においても放棄することができます。
2. 被相続人の生前の放棄
遺留分を有する推定相続人(将来の遺留分権利者)は、被相続人の生前に将来の自己の遺留分を放棄することができますが、放棄に際して家庭裁判所の許可が必要になります。
被相続人の生前に裁判所外での遺留分の放棄を認めると、被相続人や他の推定相続人等の不当な介入によって遺留分の放棄が強制されたりする事が考えられ、遺留分制度が実質的に機能しなくなる恐れがあるため、家庭裁判所の許可を要件としています。
家庭裁判所の審理では、遺留分の放棄が真に権利者の意思によるものかどうかについて、放棄の経緯等を考慮しながら、判断されます。
3. 被相続人の死後の放棄
被相続人の死後には、遺留分放棄には家庭裁判所の許可は必要とされていません。 相続発生後には、第三者の圧力によって遺留分の放棄を強制される危険性は低いからです。
(5) 遺留分の放棄と相続権
1. 遺留分の放棄の効果
遺留分の放棄は、被相続人の生前贈与や遺言による遺留分の侵害があった場合でも、その遺留分の侵害に対して減殺請求を行わないという遺留分権利者の意思表示です。
遺留分権利者が放棄したものはあくまでその遺留分だけであって、相続権の放棄ではありません。
したがって、遺留分を放棄した遺留分権利者が相続権を失うことはありません。
2. 相続放棄
遺留分権利者が、その相続権を放棄するためには、家庭裁判所にて相続放棄の手続を行うことが必要です。
(6) 遺留分を放棄すると他の相続人の遺留分に対する影響
1. 相続放棄の場合
共同相続人の一部の者が相続放棄をした場合、その分だけ他の共同相続人の相続分が増加します。
相続人が子4人の場合には、各人の法定相続分は4分の1ですが、そのうち1名が相続放棄をしたら、残り3名の法定相続分は4分の1から3分の1に増加します。相続分が3分の1に増加する結果、その3名の遺留分も各8分の1(1/2×1/4)から各6分の1(1/2×1/3)に増加することになります。
2. 遺留分の放棄
遺留分の放棄の場合は、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、 他の共同相続人の遺留分に何ら影響を及ぼしません。遺留分の放棄が被相続人の生前になされた場合でも死後になされた場合でも同様です。
3. 遺留分放棄と代襲相続
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、 その代襲相続人も遺留分を有しないものと考えられています。
代襲者は被代襲者が相続したとすれば取得したであろう相続権以上の権利を取得するものではないからです。
2.遺留分の計算
(1) 具体的遺留分
1. 遺留分割合の計算方法
遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 その他の場合は2分の1です。
2. 各相続人の遺留分
各相続人の遺留分は、 全体の遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて計算します。
3. 具体的計算例
① 相続人が配偶者と子3人である場合には、全体の遺留分は相続財産の2分の1であり、 各相続人の遺留分は、 配偶者が相続財産の4分の1(1/2×1/2)、 子がそれぞれ12分の1(1/2×1/2×1/3)となります。
② 相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、 全体の遺留分は相続財産の3分の1であり、 個別的遺留分は父母それぞれ6分の1(1/3×1/2)となります。
(2) 遺留分計算の評価基準時
1. 遺留分の基礎となる財産
各人の遺留分額は、「遺留分の基礎となる財産×個別的遺留分割合」の計算式によって算出されます。
遺留分の基礎となる財産とは、相続開始時の財産、これに加算される生前贈与や特別受益の合計ですが、これらの財産や贈与について、いつの時点を基準に評価するのかという問題が生じます。
2. 判例による評価基準時
遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時は、 相続開始の時、 すなわち被相続人死亡時を基準にすべきである、と判示しています。(最高裁昭和51年3月18日判決)
遺留分が具体的に発生するのは相続開始時であるという根拠によります。
3. 生前贈与等の評価
相続開始時の財産は、その時点での評価を行えばよいことになりますが、相続開始以前の生前贈与ないし特別受益は、贈与や受益の時点の価格を相続開始時の価値に換算しなおして計算することになります。
(3) 遺留分額の算定方法
1. 遺留分の基礎財産
遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、 その中から債務の全額を控除して算定するとしています。
贈与とは、相続開始前1年間の贈与、それより以前の贈与であっても当事者双方に遺留分権を侵害するという害意のある贈与ほか、共同相続人に対する特別受益が含まれます。
2. 遺留分額の計算
遺留分額は、遺留分の基礎財産に、個別的遺留分を乗じて計算します。
被相続人Xが妻Aと子B、Cを残して死亡し、相続財産は不動産(5500万円)と銀行預金(500万円)であったとします。またB、CのうちBのみが大学に進学し、Xから学費、生活費2000万円の贈与(特別受益)を受けていたとします。
(1)遺留分算定の基礎財産
6000万円(5500万円+500万円)+特別受益2000万円=8000万円
(2)各人の遺留分額
A 8000万円×1/2×1/2=2000万円
B、C 8000万円×1/2×1/2×1/2=1000万円
妻Aは2000万円、子B、Cはそれぞれ1000万円の遺留分があります。
つまり、基本的には、各自の遺留分額を最低限度として相続できることになります。
(4) 特別受益を受けた相続人がいる場合
1. 特別受益と遺留分
遺留分では、特別受益の規定を準用しており、特別受益財産も遺留分の算定の基礎財産となります。
もっとも、遺留分の規定上、相続開始前1年間よりも前にした贈与は、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知って(害意をもって)贈与をしたことが必要とされています。そのため、特別受益が贈与による場合には、1年前以上の贈与(特別受益)については、害意がない限り、遺留分算定の基礎とならないのではないかという問題が生じます。
2. 判例による説明
特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情の変化や相続人などの個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが特別受益相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の要件(害意)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である、と述べています。(最高裁平成10年3月24日判決)
よって特別受益は、原則として無条件に遺留分算定の基礎となり、特別受益分を加算して、遺留分侵害の有無を判断することになります。
民法 第1030条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
(5) 遺留分侵害額の計算方法
1. 遺留分侵害額
各相続人の遺留分額は、遺留分の基礎財産に個別的遺留分を乗じて算出されます。
遺留分の基礎財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、 その中から債務の全額を控除して算出します。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。
こうして計算された各相続人の遺留分額と各相続人が実際に取得した財産の金額を比較し、前者が大きい場合には、その差額分だけ遺留分侵害があることになります。
2. 具体な計算
被相続人Xが妻Aと子B、Cを残して死亡し、相続財産は不動産(5500万円)と銀行預金(500万円)で、不動産をAに、銀行預金をBに相続させる遺言を作成していた場合です。そして、B、CのうちBのみが大学に進学し、Xから学費、生活費2000万円の贈与(特別受益)を受けていたとします。
(1)遺留分算定の基礎財産
6000万円(5500万円+500万円)+生前贈与(特別受益)2000万円=8000万円
(2)各人の遺留分額
A 8000万円×1/2×1/2=2000万円
B、C 8000万円×1/2×1/2×1/2=1000万円
(3)各人の遺留分侵害額
A 5500万円の不動産を相続しており、遺留分の侵害はありません。
5500万円>2000万円
B 相続時には500万円のみを相続しているものの、生前の特別受益を加算すると、合計2500万円を取得しており、遺留分の侵害はありません。
2500万円>1000万円
C 全く財産を取得しておらず1000万円の遺留分侵害となります。
3.遺留分減殺請求権
(1) 遺留分減殺請求
1. 遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分減殺請求権の行使方法に関する規定はありません。
口頭、書面を問わず、遺留分権利者から、遺留分を侵害する受遺者や受贈者に対して、「遺留分減殺請求権を行使する」という意思表示を行えばよいことになります。
2. 遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権には、1年間の消滅時効及び10年間の除斥期間が定められていますから、受遺者、受贈者に対して、いつ遺留分減殺請求権行使の意思表示が到達したかが証明できるようにして行うのがよいでしょう。
この期間制限は法定されていますので、遺留分減殺請求の意思表示は、その発信や到達の期日を確実に証明できる配達証明書付内容証明郵便によって行うのがよいと思われます。
(2) 遺留分減殺請求の期間制限
1. 期間制限
遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。」と規定されています。
この1年の期間制限は消滅時効の期間、10年の期間制限は除斥期間と解釈されております。
2. 個別財産に対する返還請求権の時効
1年や10年の期間制限は、遺留分減殺請求権の行使のみを対象としているのか、それとも行使によって生ずる個別財産に対する返還請求の期間制限についても対象としているのかが問題となります。
この点については、遺留分減殺請求権が形成権であることを理由に、期間制限の対象は遺留分減殺請求権の行使のみに限定され、その結果生じる個別財産に対する返還請求の期間制限は、別個に考慮することとされています。
すなわち遺留分権利者は、前記1年ないし10年の期間制限内に、遺留分侵害者に対して、「遺留分減殺請求権を行使する」という意思表示をすればよく、財産の取戻しまではその期間制限内に完了する必要はないことになります。
(3) 遺留分減殺請求がなされた場合に金銭清算の可否
1. 現物返還の原則
遺留分権利者によって遺留分の減殺請求がなされると、 法律上当然に減殺の効果を生ずるため、 遺留分の侵害となる遺贈または贈与はその効力を失い、 目的物に関する権利は当然に遺留分権利者に帰属することになります。
したがって、 遺留分減殺請求権行使の結果、 受遺者または受贈者は、 対象財産の全部または一部を返還しなければなりません。
返還は現物をもってなされるのが原則で、例えば、4000万円の不動産の遺贈が行われて、遺留分侵害額が400万円という場合には、遺留分権利者は侵害者に対して、当該不動産の10分の1の持分の返還請求(10分の1の持分移転登記)を行います。
2. 価額弁償の抗弁
現物返還の原則を貫いた場合、受遺者ないし受贈者は、遺留分減殺の対象となる財産について、遺留分権利者との共有関係となる場合が生じます。
共有物の管理、使用には、共有者間での制約が生じ、共有関係の解消には共有物分割手続が必要になります。
そこで、そのような煩雑な手続きを避けるため、受遺者ないし受贈者において、遺留分侵害額相当の金銭を支払うことによって、現物返還を免れる制度が設けられています。これを価額弁償の抗弁といいます。
前記の例では、受遺者が400万円を支払うことで、10分の1の持分返還を免れることができます。
(4) 価額弁償の評価基準時
1. 価額弁償の抗弁
遺留分減殺請求権行使の結果、 受遺者または受贈者は、 対象財産の全部または一部を現物で返還しなければならないのが原則です。
ただし、受遺者ないし受贈者において、遺留分の侵害相当額の金銭を支払うことによって現物返還を免れることができ、これを価額弁償の抗弁といいます。
この価額算定の基準時はいつになるのでしょうか。
具体的には、本来はA不動産の10分の1の持分を現物返還しなければならない受遺者が、価額弁償の抗弁を主張した場合、A不動産のどの時点の価格を採用して、弁償額を決定するかという問題です。
2. 判例の考え方
価額弁償の基準時は現実に弁償がなされる時点である、と判示しました。
なお、遺留分権利者が訴訟を提起して、これに対して価額弁償の抗弁が出された場合には、現実に弁償がされる時点に最も接近した時点である、事実審の口頭弁論終結時を基準とすることも判示しています。(最高裁昭和51年8月30日判決)
前例ではA不動産の評価は、相続開始時を基準にするのでなく、弁償時もしくは、遺留分減殺請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時を基準にすることとなります。
(5) 遺留分減殺請求の対象となる財産の選択
1. 割合的減殺の原則
遺留分減殺請求の対象財産が複数存在する場合、原則として全ての財産からそれぞれの価額の割合に応じて減殺することが法律上規定されています。
すなわち、遺留分侵害額が1000万円で、遺留分減殺請求の対象となるA不動産が3000万円、B不動産が1000万円の場合、A不動産とB不動産は3対1の割合となりますから、A不動産から750万円を、B不動産から250万円を減殺する、すなわち、A、B各4分の1の持分移転登記を請求することになります。
(6) 贈与の時期による、遺留分減殺請求の差異
1. 法律の規定
遺留分減殺請求の対象となる贈与としては次のように区分して考えることが規定されています。
①遺贈
②相続開始前1年間にした贈与
③相続開始前1年間よりも前にした贈与
①及び②は、無条件に遺留分減殺請求の対象となりますが、③については、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知って(害意)贈与をした場合にのみ遺留分減殺請求の対象となる事を規定されています。
2. 特別受益との関係
共同相続人に対する贈与で、それが特別受益に該当する場合には、害意の有無を問わず、相続開始前1年間よりも前にした贈与でも遺留分減殺請求の対象になります。
(7) 遺留分減殺請求の目的物が譲渡、滅失した場合
1. 目的物の譲渡
遺留分減殺請求を行使する以前に、目的物が第三者に譲渡されることがあります。
この場合、遺留分権利者は第三者が譲渡当時、 遺留分権利者に損害を与えることを知っていた(害意)場合には、 遺留分権利者は 第三者に対しても現物返還を請求することができます。しかし、第三者が遺留分権利者に損害を与える事を知らなかった場合には、第三者(譲受人)に対して遺留分減殺請求を行使することはできず、 受遺者ないし受贈者 (譲渡人) に対して、価額の弁償を請求するしかありません。 第三者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた(害意)とは、遺留分権利者に損害を加える目的までは不要で、遺留分侵害の事実関係を客観的に認識していればそれで足りることになります。
なお、第三者に害意がある場合でも、 第三者において価額弁償によって現物返還を免れることは可能です。
2. 目的物が滅失した場合
目的物が存在しない以上、現物返還はできないため、価額弁償を請求することになります。
受遺者ないし受贈者の行為によって、目的物が滅失したり、価額の増減があった場合、価額の算定は相続開始時においてなお原状のままであるものと見なして評価することとされています。
(8) 遺贈や贈与に対する遺留分減殺の順序
1. 遺留分減殺の対象となる遺贈と贈与(生前贈与)
遺留分侵害を生じた遺贈ないし贈与(生前贈与)が一つであれば、その遺贈や贈与のみが遺留分減殺請求の対象となることは明らかといえます。
一方、遺贈と贈与が混在する場合、また贈与の時点を異にする複数の贈与が混在する場合に、遺留分減殺請求をどのような順序で行うかが問題となります。
2. 遺贈と贈与(生前贈与)の先後
遺贈と贈与が混在する場合には、遺留分権利者は、 まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません。
これは、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全と調和をはかるためです。
3. 贈与の先後
複数の贈与がある場合、 後の贈与から前の贈与に対して減殺を行うと規定されています。
贈与の先後の判断は、登記、 登録の日時でなく、契約の日時によって行われることと考えられています。
この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全と調和をはかることにあります。
(9) 複数の遺贈や、同時になされた複数の贈与に対する遺留分減殺請求
1. 遺贈、贈与に対する遺留分減殺請求
民法は、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全と調和を図っています。
具体的には、遺贈→後の贈与→前の贈与という順番で遺留分減殺がなされることになります。
では、複数の遺贈や、同時期になされた複数の贈与が存在する場合に、どのように遺留分減殺を行うべきかが問題となります。
2. 遺贈に対する割合的減殺の原則
複数の遺贈が存在する場合には、その目的の価額の割合に応じて減殺することが規定されています。
よって、遺留分権利者は、全ての遺贈を対象として、その価額の割合に応じて割合的減殺請求権を行使することになります。
例えば、甲の遺留分侵害額が1000万円で、乙へ遺贈されたA不動産が4000万円、丙へ遺贈されたB不動産が1000万円という場合には、A不動産とB不動産は4対1の割合となりますから、A不動産から800万円を、B不動産から200万円を減殺する、すなわち、甲はA、B各5分の1の持分移転登記を請求することになります。
3. 同時期になされた複数の贈与の場合
明文の規定は存在しませんが、遺贈の場合と異なる扱いをする必要はないので、同時期になされた複数の贈与全部を対象として割合的減殺を行うべきと考えられています。