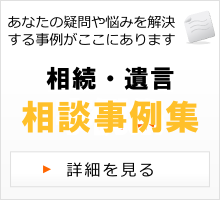相続の基礎知識
1.相続
(1) 相続
1. 権利義務の承継
相続とは、人の死亡により、亡くなった人(被相続人といいます)の権利と義務の全てが被相続人と一定血縁者(相続人といいます)に承継されることをいいます。
人の死亡によって、権利義務を持っていた人(権利の主体)がいなくなるため、新たな人へと権利義務を承継させる必要があります。
承継の対象となる権利義務とは、積極財産(不動産、動産 預貯金、株券、借地権等)だけでなく消極財産(借金、未払いの賃料、未払いの税金等)も含みます。ただし、被相続人のみに帰属した特殊な権利義務(一身専属的権利義務)は承継されません。つまり相続の対象外です。
2. 相続の発生原因
相続の発生原因となるのは人の死亡です。死亡には、自然死のほか、失踪宣告により死亡したとみなされる場合も含まれます。
失踪宣告とは、次のように定められております。
民法(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
3. 相続人の意思の尊重
人の死亡によって相続が開始しますが、相続人側の意思で、相続財産の承継をしない(相続放棄)という選択をすることもできます。相続人が相続財産を相続する自由もあれば、相続しない自由も認められています。(相続放棄等)。そうしないと、被相続人が消極財産のほうを多く残して死亡したような場合には相続人に不都合が生じるからです。
4. 遺言と法定相続
被相続人が遺言を残して死亡した場合には、遺言内容による相続が優先するため、相続手続としては遺言内容のとおりに相続手続きをする事になります。
(2) 相続の開始地
1.相続は、 被相続人の住所において開始します。
住所とは生活の拠点のことで、通常は住民登録をされている場所のことです。住所が知れないときは居所を住所とみなします。
2. 相続開始地の意義
相続開始地には、相続に関する訴訟や審判の管轄権が生じます。
相続権や遺留分に関する訴訟、遺産分割の調停や審判などは、相続開始地を管轄する家庭裁判所や地方裁判所に申し立てることができます。
また、相続税の納税地ともなり、 相続税の申告は、 相続開始地を管轄する所轄税務署に対して提出することとされています (相続税法附則3項)。
(3) 相続資格
1. 法定相続人
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続人間で法律の規定に従った相続分(法定相続分)で相続することになります。しかし、相続人間で法定相続分のとおりに相続をせず、相続財産を分ける場合(遺産分割)遺産分割協議をすることになります。
被相続人の親族の中でどの範囲の親族が相続権を有するかということが規定されています。これらの相続人のことを「法定相続人」といいます。
2. 法定相続人の順位
被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者とは法律上の配偶者(婚姻届を提出している人)のことをいい、いわゆる内縁関係の配偶者は含まれません。
第1順位の相続人は子供です。子は実子、養子いずれも含みます。ただし、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の場合は、法律上の父子関係は父親の認知によって生じるため、実態として親子関係が存在しても、父親の認知がない非嫡出子は相続人になることはできません。
第2順位の相続人としては、子(ないし子の代襲相続人)がいない場合、直系尊属が相続人となります。尊属とは自分の父母、祖父母など、自分から見て前の代の人物のことをいいます。
第3順位の相続人としては、子(ないし子の代襲相続人)、尊属もともにいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
3. 代襲相続人
法定相続人のうち、子や兄弟姉妹が相続人となる場合には代襲相続が認められています。
代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合に、それらの子(被相続人から見た場合、孫や甥、姪)が、子や兄弟姉妹が有していた相続権を承継するというものです。
子が相続人の場合は再代襲、再々代襲など何代にもわたって代襲相続が認められていますが、兄弟姉妹が相続人になる場合には1代に限って代襲相続が認められており、再代襲は認められておりません。従って、代襲相続できるのは、甥や姪までです。
(4) 代襲相続
1. 代襲相続
代襲相続とは、先代が有していた相続権を後代に承継させるという制度です。
例えば、父親の相続開始時に、その子供が既に死亡していたような場合に、その子供に父親の相続権を一切認めないとすると、本来父親が生きていれば、親→子→その子(孫)と相続されるべき流れが途切れてしまいます。
また、子が生存していて、父親の財産を相続していれば、その子から財産を相続し得たはずであるという孫の期待は保護しなければならないと言えます。
つまり、代襲相続とは、上記の例で、孫(代襲者)が親(被代襲者)を飛び越えて祖父の財産を相続するという制度です。
2. 代襲相続の要件
相続人(子ないし兄弟姉妹)が、 (1)相続開始以前に死亡したとき、(2)相続欠格に該当して相続権を失ったとき、(3)廃除によって相続権を失ったとき、の3つの場合において、その相続人の子が相続人に代わって相続することになります。
相続放棄をした場合には代襲相続は認められていません。
3. 再代襲相続
被相続人の子に代襲原因が発生すれば、 孫が代襲相続人となりますが、 その孫についても代襲原因が生じていた場合には、 孫の子(曾孫)がさらに代襲相続することになります。この場合の代襲相続を再代襲相続といいます。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。 (再々代襲・・・)
一方、 被相続人の兄弟姉妹の場合には、代襲相続のみ認められており、再代襲相続は認められていません。すなわち、代襲者は被相続人のおい、 めいに限られています。
(5) 胎児の相続権
胎児とはお母さんの体内にいる出生前の子供のことをいいます。
民法上、権利能力(権利、義務の主体となることができる能力)は、自然人と法人に認められています。ところが胎児は、相続開始時には生まれておらず、自然人として取り扱うことはできません。
自然人となっていない胎児が、相続権を有するのかどうかが問題となりますが、法律では次のように定められております。
民法 (相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児は出産によって自然人となる確率が非常に高く、胎児の時から潜在的な相続人資格を有しているといえます。また、出生の前後で相続権の区別をするならば、わずかの時間差で相続権を有する新生児と、そうでない胎児を区分することになり、不合理な差別を招くことになりかねません。
いたがって民法は、「胎児は、相続に関しては。既に生まれたものとみなす」と規定して、胎児の相続権を明確にしています。
胎児には代襲相続権も認められ、例えば、胎児の父親がその親(祖父母)より先に死亡しているときは、胎児は父を代襲することができ、祖父母の相続人となります。
(6) 相続資格の重複
1. 相続資格の重複
相続資格の重複とは、1人の相続人に相続資格が複数発生することです。
例えば、3人兄弟で長男が亡くなり兄弟相続が発生した場合、次男が3男をを養子としていた場合で、次男が先に亡くなっている場合には、 3男にはもともとの長男の兄弟姉妹としての相続資格と次男の代襲相続人としての相続資格とが重複することになります。
2. 相続分への影響
相続資格が重複する場合には、それぞれの相続資格に基づく相続分が加算されるかどうかは次のような取扱いがされております。
(1)子と代襲相続人の重複
Xに子AB、Aの子C(Xの孫)という場合で考えてみます。
XがCを養子とし、AがXの相続開始前に死亡した場合に、Cは、Xの相続において、子(養子)としての相続資格とAを代襲した相続資格とが重複します。 この場合は、子供としての相続分と、代襲相続人としての相続分を取得することができます。
(2)配偶者と兄弟姉妹の重複
Aの子XB、Xの配偶者Yという場合を設定します。
AがYを養子とした後Aが死亡し、後にXが死亡した場合に、Yは、Xの相続において配偶者として相続資格と、養兄弟姉妹として相続資格とが重複します。
この場合では、判例上相続分の加算をせず、配偶者の相続分しか取得できないことになります。
(7) 複数人が同時死亡した場合の相続関係
1. 相続の開始時期
複数名が同一事故で死亡した場合で、その死亡開始時期の前後が不明であるような場合にはどのように取り扱うのでしょうか?
例えば、Aさん(配偶者は死亡)子共がDさん、Dさんの妻がEさん。Aさんの弟がCさんとします。同一事故でADが死亡した場合、Aさんが先に死亡したとすれば、Aさんの相続人はDさんのみになるため、A→D→Eと相続することになり、CさんがAさんを相続することはありません。
ところが、Dさんが先に死亡したすれば、Dさんの相続においては、Eさんと尊属のAさんがDさんの相続人となり、その後のAの相続においては、兄弟姉妹としてCさんがAさんの相続人となることから、D→E、D→A→C、という相続関係になります。
このように、死亡の前後により、相続人の範囲や順位について大きく差が出ることになります。
2.同時死亡の推定
このように、死亡の前後で相続関係に大きく差が出るため、民法上、数人のうち、先に死亡した者が明らかでない場合には、それらの者は同時に死亡したものと推定することが規定されています。この規定により、同時死亡者間では互いに相続が発生しないことになります。
従って、AD間相互に相続が発生することはなく、Aさんの相続人はCさんのみとなり、Dさんの相続人はEさんのみとなります。
民法(同時死亡の推定)
第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する
2. 相続欠格、廃除
(1) 相続欠格
1. 相続欠格
相続権を有する相続人が、不正に相続を発生させようとしたり、不正に自己の相続分を多くしようとした場合、そのような相続人に他の相続人と同様に相続権を認めることは正義、公平の観点から許されません。相続欠格とは、そのような不正行為があった場合に相続権を剥奪するという制度です。
2. 欠格事由
被相続人や他の相続人への生命侵害に関する行為や不正な遺言への干渉行為を規定しています。
(1) 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
(2) 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
(3) 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者。
(4) 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
(5) 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
3. 相続欠格の効果
欠格事由に該当する行為をした者は、何の手続も要せずに、相続権を剥奪されます。
相続欠格の効果は、欠格事由に該当する行為をした対象の被相続人との関係でのみ生じるものです。
なお、欠格者の子が欠格者を代襲して相続人となることは認められています。
(2) 相続の廃除
1. 推定相続人の廃除
廃除とは、遺留分を有する推定相続人(将来相続人となることができる者)が被相続人に対する虐待や侮辱等を行った場合で、被相続人がその者が相続する事を望まない場合に、その者の相続権を奪うことです。
相続欠格と異なり、家庭裁判所の審判を得て初めて廃除されることとなります。
2. 廃除の対象者
廃除の対象者としては、遺留分を有する推定相続人です。具体的には、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹は含まれません。
遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)については、被相続人が遺言を作成し、その者への相続を認めない条項を設ければ廃除と同じ効果が得られます。
3. 廃除事由
(1)被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたこと
(2)その他の著しい非行があったこと
廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断するため、個々の事案ごとに、虐待や侮辱、非行の程度が相続権の剥奪という効果に見合う重大なものであったかどうかが判断されます。
4. 廃除の効果
家庭裁判所で廃除を認める審判が下されたり、廃除を認める調停が成立すると、当該相続人はその相続権を失います。
被相続人の死亡後に廃除の審判を得た場合でも、被相続人の死亡時(相続発生時)にさかのぼって相続権を失います。
なお廃除は、廃除を申し立てた被相続人との関係でのみ生じるものです。
(3) 廃除の取り消し
1. 一度行った廃除の取消し
廃除とは、被相続人に対する虐待や侮辱等があった場合に、被相続人において、遺留分を有する推定相続人の相続権を否定したい場合に、家庭裁判所に申し立てるという制度です。
廃除そのものが、被相続人の意思を尊重するという制度ですから、被相続人が一度行った廃除を取消したい場合には、家庭裁判所に申し立てることによって取り消すことができます。
2. 廃除の取消しの手続
廃除の取消しは、被相続人が家庭裁判所に取消しの請求をすることになります。廃除の取消しは遺言によってもすることができますが、その場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の取り消しを請求します。
3. 廃除の取消しの効果
廃除の取消しの審判が確定すると、廃除された推定相続人はその相続権を回復します。
廃除の取消しの審判が、被相続人の死後になされた場合でもその効果は遡及し、当該相続人は、相続開始時から相続権を有していたことになります。
(4) 相続欠格者の宥恕(ゆうじょ)
※ (宥恕とは、寛大な心で罪を許すこと)
1. 相続欠格者の宥恕
相続欠格とは、被相続人や他の相続人への生命侵害行為や遺言への不当な干渉行為を行った相続人の相続資格を剥奪するものです。欠格の効果は、法律上当然に発生し、特段の手続を要するものではありません。
では、被相続人の意思で、相続欠格者を宥恕して、相続資格を回復させることができるかどうかが問題となります。
2.宥恕について、肯定説、否定説
否定する考え方と肯定する考え方があります。つまり、宥恕には否定説と肯定説のいずれもが存在します。
肯定説(宥恕できる)
①被相続人は相続資格を有しない全くの他人に対しても、生前贈与や遺言によってその財産を承継させることができ、もともと財産処分の自由が広く保障されている。
②被相続人の意思によって、相続欠格者の相続資格を回復させたいと考えるならば、それを認めることが被相続人の財産処分の自由を認めることとなる。
否定説(宥恕できない)
①相続欠格は法律上当然の相続資格喪失事由である。
②相続欠格事由として公益を著しく害する行為が規定されている。
③そもそも民法に宥恕についての明文の規定が存在しない。
以上により、肯定説、否定説がありますが、宥恕を認める肯定説が多数説です。
3. 宥恕の手続
宥恕の手続については法律上の規定がありません。
被相続人が、相続欠格者の欠格事由を認識した上で、これを許し、相続人として処遇する旨の意思又は感情の表示があればよいと考えられています。
被相続人が相続欠格事由の発生したことを知りつつ、 欠格者に対する遺贈を行った場合なども、 宥恕がなされたと判断して、 そのような遺言条項は有効であると考えられています。
3. 相続の承認、相続放棄
(1) 相続の承認
1. 単純承認
相続が開始した場合、相続人には3つの選択肢(単純承認、限定承認、相続放棄)があります。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無条件で相続することを認めることです。
2. 法定単純承認事由
法定単純承認事項として規定されている事由は次の3つです。
①相続人が相続財産の一部又は全部を処分したとき。
②熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。
③限定承認、相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
3. 単純承認の効果
単純承認により、各相続人はその相続分の割合で、被相続人の権利及び義務を無条件で承継します。
(2) 相続の承認
1. 限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきこととする相続のしかたです。
つまり、被相続人に積極財産(プラスの財産)もあるが、消極財産(マイナスの財産)も相当あり、相続財産が全体でプラスになるのかマイナスになるかわからないという場合に利用するメリットがあると思われます。
2. 限定承認の手続
限定承認を行うことが出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内です。(この3ケ月の期間の事を熟慮期間といいます。)通常は被相続人の死亡時から3ケ月となります。
熟慮期間内に相続の放棄や限定承認をしなかった場合、法定の単純承認事由が発生した場合には、相続を単純承認したものとみなされます。
相続人が複数人存在するときは、相続人全員が共同して限定承認をしなければなりません。したがって、相続人の一人でも単純承認をした場合には、他の相続人は限定承認をすることができなくなります。
限定承認は家庭裁判所にその旨の申述書及び財産目録を提出して行います。
3. 限定承認の効果
限定承認をした相続人は相続財産の範囲内でのみ被相続人の消極財産(マイナスの財産)の支払いを行い、プラス財産が残ればその分を相続することができます。
(3) 相続放棄
1. 相続放棄
被相続人が死亡して相続が開始した場合、相続人が何もしなければ、相続人は単純承認したとして、無条件に被相続人の積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)も承継します。
消極財産つまり、借金や保証債務のほうが多い場合には相続人側において相続するメリットは無いと思われます。また、相続による財産の取得を望まない相続人がいる場合もあります。つまり、相続人としても、財産を相続する自由が認められているのと同様に、相続しない自由も認められなければなりません。
相続人にも、相続財産を取得するか、取得しないかを判断する自由があります。
そこで、相続人の意思によって、相続を放棄するという制度があります。
2. 相続放棄の手続
相続放棄を行うことが出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内です。(この3ケ月の期間の事を熟慮期間といいます。)通常は被相続人の死亡時から3ケ月間となります。
熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合や、法定の単純承認事由が発生した場合には、相続を単純承認したものとみなされます。
相続放棄は、家庭裁判所にその旨の申述書を提出して行います。
3. 相続放棄の効果
相続放棄を行えば、相続放棄者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の権利義務を一切承継しないということになります。また、放棄者が初めから相続人でなかったとみなされるため、他の相続人の相続分が変化することがあります。
(4) 相続の承認、放棄の熟慮期間の延長
1. 熟慮期間
相続の承認や放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
通常は、被相続人の死亡の時からの3ケ月間が熟慮期間となります。
相続人は、 この熟慮期間内に相続財産の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかの選択を行うことになります。
相続人が何もしないまま3ケ月の期間が経過すると、 相続放棄や限定承認をすることができず、相続の単純承認をしたものとみなされます。
2. 熟慮期間の延長
熟慮期間は、家庭裁判所の審判によって延長することができます。
熟慮期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、 相続の承認や相続放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合等に認められています。
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、 期間経過後の申立てはできなのが原則です。
(5) 相続の放棄や承認の撤回、取り消し
1. 熟慮期間の存在
相続の承認及び相続放棄は、熟慮期間内であっても撤回することはできません。 たとえ熟慮期間内であっても、一方的な撤回をすることができるとすれば、相続に関する法律関係を不安定にするため、撤回は認められていません。
取消しは、撤回と異なり、相続の承認及び放棄がなされた後でも、詐欺や脅迫等の取消原因がある場合には、 取消しを行うことが認められています。
民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
4.相続人の不存在
(1) 相続人が誰もいない場合
1. 相続人の不存在
相続発生時に、被相続人に相続人がいない場合や、相続人はいるけれども全員が相続放棄をしてしまったような場合で、相続人が誰もいない場合には相続人不存在となります。
2. 相続人不存在の場合の手続
被相続人の財産は相続財産法人となり、家庭裁判所によって、相続財産管理人が選任されます。
その後、官報等により相続の発生、相続財産法人を告知する公告を行います。その後債権者に対する公告と相続人に対する公告を行います。
債権者に対する公告とは、相続開始の告知により、被相続人に対して債権を有していた債権者に届出をしてもらい、相続財産からその債権の弁済をする手続です。
相続人に対する公告とは、相続開始の告知により、本当に相続資格を有する者がいないのかどうか最後の発見の機会を与える手続です。この期間内に相続人として届出をしなければ、相続人としての資格から除斥され、相続人の不存在が確定することになります。
3. 特別縁故者への分与
相続人不存在が確定後、特別縁故者(相続人ではないが、相続人と特別な関係を有していた者)がいる場合、その者からの請求により、家庭裁判所の判断で相続財産の一部または全部を分与することができます。
4. 相続財産の国庫帰属
相続財産の清算、特別縁故者への財産分与がなされない残余の相続財産があるときは、国庫に帰属することになります。
(2) 特別縁故者への財産分与
1. 特別縁故者
特別縁故者とは、法定の相続人ではないけれども、内縁の配偶者であったり、事実上の養子、被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養介護に努めていたりするなど、被相続人と特別の関係があった者のことです。
2. 特別縁故者の相続資格
被相続人が、特別縁故者へ財産を遺贈する遺言を残していた場合には、特別縁故者は財産を承継することができます。
被相続人が遺言を残していなかった場合には、特別縁故者は法定の相続人ではないので、財産を承継することはできません。
法定の相続人が誰もいない、つまり相続人不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与という制度があります。
3. 財産分与手続
相続人不存在の場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任した上で、相続人捜索のための公告を行います。この公告を行っても相続人が現れないときに相続人の不存在が確定します。
財産の分与を受けたいと思う特別縁故者は、公告期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して財産分与の請求をしなければなりません。この期間内に請求をしなければ、相続財産はそのまま国庫に帰属します。
5. 法定相続分
1. 法定相続分
法定相続分とは、法定相続人が有する相続分の割合のことで、民法で具体的な割合が規定されています。
2. 具体的割合
相続人が1人の場合は、法定相続分は100%(1分の1)となります。
相続人が配偶者と子の場合には、配偶者2分の1、子2分の1となります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
同順位の相続人が複数いる場合は、各人の相続分は均等となります。
3. 遺言による相続分の指定
遺言によって法定相続分と異なる特別の相続分の指定を行うことができます。これを指定相続分といいます。
この場合には、指定相続分の割合が法定相続分に優先することになります。
6. 特別受益
(1) 特別受益
1. 特別受益
相続人が、婚姻、養子縁組のためや生計の資本として、被相続人の生前に被相続人から財産の一部を譲り受けていた場合(特別受益といいます。)、そのような財産の取得を相続分の前渡しと同様に考え、相続分を算定する上で考慮する必要があります。
2. 計算方法
相続開始時の財産に、特別受益財産を加算して(加算する事を特別受益財産の持ち戻しといいます。)、生前に渡された財産分を含めた実質的な相続財産の額を算出します。この実質的な財産額をみなし相続財産といいます。
次に、みなし相続財産に各人の相続分を乗じて、各人の相続する取得分を計算します。
この取得分から、特別受益財産額(財産の前渡分)を控除した分が、相続の際に取得する具体的相続分となります。
3. 具体例
遺産4000万円、子ABのうち、Bのみ被相続人の生前に2000万円の特別受益(相続財産の前渡し)があったという場合、
みなし相続財産の計算 4000万円+2000万円=6000万円
各人の相続分 6000万円×1/2より3000万円
相続時のAの相続分 3000万円
相続時のBの相続分 3000万円-2000万円=1000万円
特別受益額が各人の取得分を超過しているとき
(Bが生前5000万円の特別受益を受けていた場合)
みなし相続財産の計算 4000万円+5000万円=9000万円
各人の相続分 9000万円×1/2より4500万円
相続時のAの相続分 4000万円
相続時のBの相続分 0
Aは本来の相続分4500万円より、500万円少ない4000万円しか取得できませんが、この500万円をBがもらい過ぎとしてAに支払いをする必要はないというのが通説判例です。
(2) 特別受益持戻しの免除
1. 特別受益の持戻し
相続人のうち一部の相続人が特別受益財産を得ていた場合、相続人間の公平をはかるため、その特別受益分を加算して具体的相続分の算定を行います。これを特別受益の持戻しといいます。
具体的には次のようになります。
①(相続開始時の相続財産価額)+(特別受益額)=みなし相続財産額
②(みなし相続財産額)×(法定または指定の相続分)=各人の本来の相続分
③特別受益者以外の相続人 ②で計算した相続分
特別受益者の相続分 ②で計算した相続分-(特別受益額)=具体的相続分
2. 特別受益の持戻しの免除
特別受益の持戻しは相続人間の公平を図るのと同時に、 被相続人の合理的意思を推測した算定方法ですから、 被相続人が持戻しを希望しない場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されません。すなわち、相続開始時の相続財産価額に特別受益額を加算して計算する、みなし相続財産額の計算は行わず、相続開始時の相続財産価額のみを相続財産として計算します。
3. 特別受益の持戻しの免除の方式
被相続人の特別受益に関する持戻免除の意思表示によって免除できます。
持戻免除の意思表示は、生前行為によっても、 遺言によっても行うことができます。
7. 寄与分
(1) 寄与分
1. 寄与分
寄与分とは、相続財産の維持増加に通常期待される程度を超える貢献、つまり特別の寄与があった場合、共同相続人間の実質的公平を図るため、相続財産の一定割合または金額を控除して、これを当該相続人が相続分とともに受け取る制度をいいます。
たとえば、長男が飲食店を営んでいる父を助けてその商売の発展継続に貢献した結果、財産が大きく増えた一方で、二男はサラリーマンとして独立していたという場合には、父親の遺産の増加に長男は大きく貢献していたことになります。
父親の相続の際に長男の貢献を財産として評価を行い各自の相続分を計算することになります。
2. 寄与分が認められる場合
寄与分は相続人にのみ認められ、内縁配偶者や長男の妻には認められません。
また、寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)があることが必要で、扶養義務の範囲内で貢献をしたとしても寄与分は認められません。また寄与について既に相当の対価を得ている場合にも特別の寄与とは評価されません。
3. 手続
寄与分は、まず、共同相続人の協議で定めることになっています。
共同相続人の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が審判で定めます。寄与分の審判の申立ては遺産分割の手続の中で行うこととなっています。
(2) 寄与分がある場合の相続財産
1. 寄与分がある場合の具体的相続分の算定方法
寄与分がある場合、各人の具体的相続分は以下のように算出します。
①(相続開始時の財産-寄与分)=みなし相続財産
②(みなし相続財産)×(各人の指定ないし法定相続分)=各人の相続額
③ 寄与者の相続分(②で計算した各人の相続額)+(寄与分)=寄与者の相続額
④ 寄与者以外の相続分 ②で計算した各人の相続額
となります。
2. 具体例
相続人が甲乙2人の子供である場合、相続開始時の財産5000万円、甲の寄与分1000万円という事例では次の計算例によります。
(1)みなし相続財産 5000万円-1000万円=4000万円
(2)各人の相続額 4000万円×1/2=2000万円
(3)甲の相続額 2000万円+1000万円=3000万円
乙の相続額 2000万円