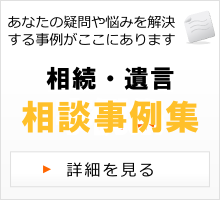遺産分割の基礎知識
1.遺産分割
(1) 遺産分割
1. 遺産分割について
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の開始によって、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態になります。そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要になります。これを遺産分割といいます。
2. 遺産分割の当事者
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効になります。
3. 遺産分割の基準
遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると法律上規定されています。
4. 遺産分割の方法
現存する遺産を各相続人に分割することを現物分割といいます。
遺産を売却して売却代金を分配するという換価分割や、一人が遺産を多く取得する代わりに過不足分を他の相続人に対する現金の支払い等で精算するという代償分割という方法があります。
民法(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(2) 法定相続分と異なる遺産分割協議
1. 法定相続
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。法律上、相続人の種別や順位に応じて法定相続分という一定の割合が規定されており、遺産分割協議を行う際の一つの基準となっております。
2. 積極財産
遺産のうち、積極財産(プラスの財産)については、相続人全員の合意があれば、各相続人の法定相続分を無視して自由に遺産分割協議をすることができます。
遺産分割とは、被相続人の死後、相続人全員の共有状態にある遺産をどのように分けるかを決定する手続きですから、共有者全員がその遺産分割に納得するのであれば、どのような分割方法を決めてもかまわないからです。
3. 消極財産
遺産のうち、消極財産(マイナスの財産)については、債権者がいます。
各相続人の資力が異なる場合、債権者から見れば、自分の知らないところで資力の少ない相続人を債務の承継者と決められてしまっては不都合が生じます。
よって、消極財産については、原則として法定相続分に従った分割をする必要があり、法定相続分と異なる分割を行いたい場合には、個別に債権者と合意する必要があります。
(3) 遺言と異なる遺産分割
1. 相続人全員が遺言の存在、内容を知っている場合
被相続人は遺言で、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈等を行って、遺産の分け方を自由に決定することができます。
もっとも、遺言は被相続人が単独で作成できるため、遺言者がよかれと思って書いた遺産の分け方が、相続人にとっては逆に望ましくないという場合もでてきます。
相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺産について遺言とは別の分割方法を合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能と思われます。
2. 遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立してしまった場合
一部の相続人が遺言書を隠匿していたため、そのような事態に至った場合には、当該相続人は相続資格の欠格となります。
よって、先に完了した遺産分割は本来相続資格を有しない者が遺産分割協議に参加したことになるため無効となり、その後、相続欠格者を除外して遺言の執行や再度の遺産分割協議を行うことになります。
相続人の全員が遺言書の存在や内容を知らなかったときには、遺産分割の結果が遺言による相続よりも有利になる相続人、不利になる相続人がでてくると思われます。そうなると、やはり遺言の執行や遺産分割協議を再度行うことになるでしょう。
(4) 遺産分割の期限
1. 遺産分割の時期
遺産分割は、相続開始後いつでも行うことができます。
遺産分割に時期的な制限はありません。また一定期間の経過によって遺産分割を行う権利が消滅することもありません。
2. 遺産分割の禁止
被相続人が遺言、家庭裁判所の調停や審判、相続人全員の合意によって、一定期間遺産分割を禁止することができます。
この場合には、その期間は遺産分割をすることができません。
(5) 遺産分割の禁止
1. 遺産分割の時期的制限
遺産分割は、相続開始後いつでも行うことができると規定され、時期的な制限は存在しません。しかし、被相続人において、相続人が若年であるため判断力が成熟するのを待ちたい場合などは、一定期間遺産分割を禁止する実益があると思われます。
2. 遺言による遺産分割の禁止
被相続人は、 遺言で5年以内の期間を定めて、 遺産の全部又は一部についてその分割を禁止することができます。
遺産分割の禁止は、遺言で行わなければならず、 それ以外の生前行為で指定することは認められません。
3. 家庭裁判所による遺産分割の禁止
遺言によって、遺産分割が禁止されていない場合であっても、相続開始後に「特別の事由」がある場合には、家庭裁判所は、遺産の全部又は一部について、期間を定めて分割を禁じることができるとされています。
4. 相続人間の合意による遺産分割の禁止
相続人全員が合意すれば、遺産分割を禁止することができます。
遺産分割は遺産共有状態の解消を目的とした各遺産の配分手続ですから、その共有者全員が、合意によって、共有状態の解消を先延ばしにすることを認めてもかまわないからです。
(6) 遺産分割の当事者
1. 遺産分割協議の当事者
遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。
ところが、遺産分割協議を行う場合に、相続人の一部の者が行方不明である場合があります。このような場合、財産管理人等の選任を行い、遺産分割を行わなければなりません。
2. 不在者財産管理人の選任
行方不明者が生死不明であっても、失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たさない場合や、生きていることははっきりしているが単に行方不明であるというような場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てます。
3. 不在者の財産管理人選任後の遺産分割手続
不在者の財産管理人が選任された後、行方不明者の代理人として、この財産管理人を加えて遺産分割協議を行います。
不在者の財産管理人による遺産分割協議は、財産の処分行為であるため、不在者の利益を害さないように、裁判所の許可が必要とされています。家庭裁判所の許可にあたっては法定相続分を遵守した遺産分割内容が求められることが多いでしょう。
4. 失踪宣告
行方不明者が失踪宣告の要件を満たす場合には、失踪宣告の申立てを検討します。失踪宣告とは、人が生死不明のときに、利害関係人の申立てによって、家庭裁判所が失踪の宣告を行い、不明者について死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告の要件は次のように規定されております。
①生死が7年以上不明な場合
②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したもので、各1年以上生死不明な場合
5. 失踪宣告後の遺産分割手続
家庭裁判所により失踪宣告がなされれば、行方不明者は死亡したものとみなされますので、残りの相続人で遺産分割協議を行うこととなります。ただし失踪宣告によって代襲相続が発生する場合は、その代襲相続人を加える必要があります。
(7) 相続人に未成年者がいる場合
1. 未成年者の判断能力
遺産分割は、誰がどのように遺産を取得するのかを決定する手続です。
権利義務の変動をもたらす重要な協議であり、自己の取り分を巡って相続人間の利害が対立しやすいともいえます。
2. 未成年者の法律行為
未成年者は父母の親権に服します。
親権者は、子の財産に関する法律行為を代表(代理)すると定められているため、未成年者が当事者となる遺産分割は、親権者が法定代理人として、未成年者を代理します。
3. 法定代理人が参加しなかった遺産分割協議の効力
法定代理人が参加しない、あるいは未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った遺産分割協議は取消すことができます。
(8) 未成年者と法定代理人が利益相反する場合
1. 利益相反
未成年者が相続人の場合、遺産分割協議には通常、法定代理人(親権者)が未成年者を代理して参加することになります。
これは未成年者保護のための規定ですが、法定代理人と未成年者の利益が相反する場合には、これとは別個の手当てが必要となります。
2. 利益相反の具体的場面
(1) 未成年者、法定代理人いずれも相続資格を有する場合
例えば夫Aが、妻Bと未成年の子Cを残して死亡した場合、相続人はB、Cとなり、この2名で遺産分割協議を行うことになります。
この場合、BがCを代理できるとなれば、Bが自らの相続分を多く、Cの相続分を少なくするという危険性が生じます。
(2) 法定代理人が複数人を代理する場合
例えば、夫Aが、妻Bと未成年の子C、Dを残して死亡したのち、夫の父親E(C、Dの祖父)が死亡した場合、C、DがAを代襲してEの相続人となります。
Eの相続についてBは相続資格を有しませんが、C、D双方を代理できるとなれば、Cの相続分を多く、Dの相続分を少なくするという不正を行う危険が生じます。
3. 特別代理人
利益相反の場面では、法定代理人は未成年者を代理することができません(前記(2)では1人の子の代理しかできません)。
そこで、法定代理が不可能な未成年者については、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があります。そして、母親Aと子B、子Cで遺産分割協議を行う場合には、利益相反となり母親Aは子B、子Cを代理できませんので、子B、子Cにそれぞれ1人づつの特別代理人を選任しなければなりません。
(9) 遺産分割後に被相続人が認知した子
1. 死後認知
婚姻関係にない男女間に生まれた子について、母子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父子関係は認知によって生じます。
そのため、父親の認知がない非嫡出子が父親の相続権を得たいという場合、非嫡出子側で認知請求を行う必要があります。
認知の訴えは、父親の生前あるいは父親の死後でも3年以内ならば提起することができます。そのため、認知請求が裁判で認められた時には、既に父親の遺産分割が完了していることがあります。
認知の効力は、出生のときに遡るという遡及効が定められていますが、この遡及効を徹底すれば、既に完了した遺産分割は一部の相続人を除外してなされたことになるため、効力が認められないのではないかという問題が生じます。
2. 価額による支払請求
死後認知によって相続人となった者が、遺産の分割請求をするにあたり、 他の相続人が既に遺産分割その他の処分をしている場合には、価額による支払請求のみが認められています。
先になされた遺産分割は、その時点では一応相続人全員の関与があったわけですから、やり直しまでを認める必要がないからです。
民法(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
(10) 遺産分割の手続
1. 遺産分割協議
遺産分割の必要がある場合、相続人全員での遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、話合いによって各人がどの財産を取得するかを決定し、その結果を遺産分割協議書という書面に記載して、相続人全員の実印と印鑑証明を添付するのが通常です。
2. 遺産分割調停
裁判所外で、遺産分割の協議ができない時、または協議が調わない時には、家庭裁判所に対して、相続人全員を当事者とする遺産分割調停の申し立てをすることができます。
調停とは、裁判官と調停委員2名が相続人の間に入り、話合いで遺産分割協議をまとめようとする手続です。話合いによる合意が必要な点は、裁判所外での遺産分割協議と異なりませんが、第三者の意見が入ることにより、合意が成立する可能性は高くなると言えます。
調停が成立すると、各人がどの遺産を取得するかが調停調書に記載され、その内容は確定審判と同様の効力を有します。
3. 遺産分割審判
遺産分割審判は、審判官による審判によって、遺産を強制的に分割する手続です。
遺産の現物分割が困難な場合には、換価分割(遺産を売却して売却金を分配する方法)、代償分割(一人が遺産を多く取得する代わりに過不足分を他の相続人に対する現金の支払い等で精算する方法)も認められています。
(11) 相続人の一部を除外したり、相続人でない者を加えて成立した遺産分割協議
1. 遺産分割の当事者
遺産分割の当事者は、相続資格を有する相続人です(代襲相続人や包括受遺者を含みます)。
遺産分割は、相続人間で共有状態にある遺産を、具体的に分割するという手続ですから、その共有持分権を有する全員が参加する必要がありますし、共有持分権を有しない者が参加することはできません。
よって、相続人の一部を除外したり、相続人でない者を加えて成立した遺産分割協議は無効となります。
この場合、相続人全員を当事者とした上で、再度の遺産分割協議を行う必要があります。
2. 死後認知の例外
もっとも、相続開始後認知によって相続人となった者は、既に完了した遺産分割の無効を主張することはできず、 価額による支払のみを求めることになります(民法910条)。
2.遺産の評価
(1) 遺産の評価
1. 遺産の評価の必要性
遺産分割を行う前提として、そもそも遺産の全体がいくらなのか、遺産を構成する各財産の評価はいくらなのかを明らかにしないと、各自が取得することになる財産が各自の相続分に近いのかそうでないのかということや、遺産分割の内容が納得できるものなのかということを判断することができません。
現金や預貯金の場合には、評価は額面どおりとなります。上場株式については、遺産分割時の取引市場の価格、あるいは遺産分割に直近する一定期間における取引市場の平均価格によることで、算出が可能になります。
遺産の土地については、例えば、公示価格を基準にする場合や、近隣の取引事例を基準にする、その土地の収益性(賃料収入)を基準にする場合などが考えられます。路線価や固定資産税評価額といった公的な価格を基準にする等の方法も考えられます。
(2) 遺産の評価の基準時
1. 遺産の価値の変動
遺産分割に際して、各相続人がどれだけの財産を取得するのかというのは非常重要なことがらです。
例えば株式のように、どの時点かによって価値が大きく変動するものについて、いつの時点を基準に評価をするべきかという問題が生じます。
すなわち、相続発生時には高価であった株式が遺産分割時にはほとんど無価値になっていたり、あるいはその逆のことが生じる可能性もあり得ます。
2. 遺産分割の基準時
遺産の評価時点としては、相続発生時(被相続人の死亡時)なのか、それとも遺産分割が現実に行われる時(遺産分割時)なのかという2つの考え方があります。
相続発生後、直ちに遺産分割協議がなされるとは限りませんし、仮にすぐに遺産分割協議をはじめた場合でも、調停、審判を経る間に数年が経過してしまうこともあります。
遺産の配分は遺産分割協議によって確定し、それによって各相続人が単独で取得財産の所有権を得ることになります。とすれば、遺産の評価も単独で有効な処分権限が認められない相続発生時よりも、処分権が発生する遺産分割時を基準にするほうが公平といえます。
そのため、遺産の評価は、遺産分割が現実に行われる時を基準にする場合が多いようです。
(3) 株式の配当や不動産賃料の取り扱い
1. 元本と収益
被相続人が株式や不動産を所有していた場合、これらを元本として、配当や賃料等の収益が発生することがあります。
相続発生前に生じていた収益は、現金ないし金銭債権として遺産分割の対象となることは明らかですが、相続発生後に生じる収益は遺産分割においてどのように扱うかが問題です。
すなわち、現実の遺産分割においては、 相続開始から分割完了までに相当の時間を要することも多く、その間の収益の帰属や、遺産分割で結果的に元本を取得した相続人が、遡ってその収益を取得できるのかという点が問題となります。
2. 最高裁平成17年9月8日判決
(1) 相続発生から遺産分割までの間に、遺産である不動産を賃貸して得られる賃料は遺産とは別個の財産である。
(2) 不動産から生じる賃料(賃料債権)については、各相続人はその相続分に応じ、分割単独債権として確定的に取得する。
(3) 各相続人が確定的に取得した賃料(賃料債権)は、後になされる遺産分割によって当該不動産の承継者が決定した場合でも、影響を受けない。
3.合意による収益の分割
上記判例は、相続財産から得られる収益について、別途相続人間で遺産分割協議の対象とする合意を排除する趣旨ではないと考えられています。すなわち、相続人全員の合意があれば、 遺産分割協議において相続財産とその収益とを一括して遺産分割協議をすることも可能と考えられています。
3.遺産分割に関する問題
(1) 遺産分割完了前の銀行預金
1. 銀行預金の性質
預金とは、顧客が銀行に対して、金銭の引出しを請求できるという金銭債権です。
単純な金銭債権であるため、相続が発生した場合には、可分債権として当然分割され、各相続人がその相続分に応じて権利を承継すると考えられています(最高裁昭和29年4月8日判決)。
この理論を徹底すると、各相続人は遺産である預金について、遺産分割完了前に、単独でその相続分に応じた金額の引き出しをすることができることになります。
2. 遺産分割の実務
現実の遺産分割では、銀行預金を遺産目録に明記し、どの相続人に配分するかを決定するのが通常で、遺産分割前に各相続人がその相続分に応じた銀行預金の引き出しを請求をすることはありません。
3. 銀行実務
銀行実務では、相続人の1人がその相続分だけ払戻しを請求しても応じてくれません。
銀行側としては、払戻請求者が真実の権利者でなかった場合に相続人間の紛争に巻き込まれるリスクがあるからです。
そのため払戻の際には、銀行側が、相続資格の証明書類(戸籍等)に加え、相続人全員による遺産分割協議書あるいは払戻同意書と各相続人の印鑑証明書の提出を求めることが一般的です。
(2) 相続人の一人が不動産を独占的に使用、収益している場合
1. 相続人の1人による遺産の占有
相続人の1人が、他の相続人の同意なく、被相続人の遺産を独占的に使用、収益することがあります。この場合、他の相続人は、明渡請求や損害賠償請求をすることができるか問題となります。
2. 明渡請求
遺産分割完了までの間、被相続人の所有していた遺産は、共同相続人の共有となります。そして、共有者の1人が共有物を勝手に占有、使用している場合でも、各共有者はそれぞれの共有持分権に基づいて共有物の全部を使用する権限をもっているので、他の共有者といえども、全面的にその使用収益を排除することはできないとされています(最高裁昭和41年5月19日判決等)。
従って、遺産である不動産を独占している相続人に対して、他の相続人は当然には明渡を求めることはできません。
3. 賃料相当の損害金の請求
遺産である不動産を独占している相続人が、自己の相続分にもとづく使用収益の範囲を超えて利益を得ている場合については、他の相続人は、不当利得ないし損害賠償を根拠に、各人の相続分に基づいた相応の金銭(賃料相当損害金)の支払を求めることができます。
(3) 遺産分割前の遺産の処分
1. 遺産共有状態
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、遺産は相続人全員の共有状態となり、遺産分割手続によって共有状態の解消を行うことになります。
遺産共有状態にある個々の物や権利を遺産分割前に処分しようという場合には、共有物に関する規定に従うことになります。
2. 相続人全員の同意
遺産分割前の個々の遺産の処分は、原則として、相続人全員が共同して処分行為を行わなければなりません。ただし、 処分行為を現実に相続人全員が行うことまでは必要とされず、 処分行為を行う者以外の相続人全員の同意があれば足りると解されています。
そのため、処分に反対する相続人が一人でもいる場合には、 遺産分割を請求するほかはないことになります。
3. 個々の持分の処分
各相続人は、 遺産分割前に遺産に属する個々の物や権利について、その相続分に応じた持分権を有しており、 この持分の限度において、持分権を単独で処分することは認められています。
すなわち、相続分が2分の1の場合には、遺産分割前であっても、遺産に属する個々の物や権利について、2分の1の持分の限度においては、単独で処分することができるのです。
相続人の一人がその持分を第三者に譲渡した場合、 譲渡された持分は、 遺産分割の対象から外れます。そのため、 持分の譲受人が他の相続人との共有関係を解消したいと考える場合には、遺産分割の手続によるのではなく、 共有物分割の手続によることになります。
4.遺産分割の効力
(1) 遺産分割の遡及効
1. 遺産分割の遡及効
遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、 各相続人が分割によって取得した財産は、 相続開始時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。
遡及効が認められる範囲は、 遺産分割によって分割した遺産に限られます。
例えば、代償分割によって取得した遺産については遡及効は生じますが、 代償金支払債務について遡及効は生じません。換価分割によって取得した代価についても遡及的効力は生じません。
2. 第三者の権利保護
相続開始から遺産分割の完了までは時間を要することが多く、一部の相続人がその間に、特定の相続財産について自己の持分を第三者に譲渡してしまうことも考えられます。
このような場合において、第三者への譲渡を無視した遺産分割が後に行われ、かつその遺産分割に遡及効が認められてしまうとなれば、第三者への譲渡も遡って効力を失うことになってしまいます。
そこで、相続発生後遺産分割前に、相続人から権利を譲り受けた第三者を保護するため、 遺産分割の遡及効によっても第三者の権利を害することはできないと規定されています。
3. 対抗要件
しかし、第三者において遺産分割の遡及効の制限を主張するためには、譲り受けた相続財産(ないしその持分)について、登記等の対抗要件を備える必要があります。
(2) 成立した遺産分割の再度の遺産分割協議
1. 遺産分割の合意解除
相続人の一部の人だけがやり直しを考えても、無効、取消事由がない限り、一度行った遺産分割の効力が覆ることはありませんが、相続人全員が合意して当初の遺産分割とは異なる再度の遺産分割を希望した場合には可能となります。
2. 最高裁平成2年9月27日判決
共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、 改めて遺産分割協議をなしうることは、 法律上、 当然には妨げられるものではない、と判示し、 合意解除の有効性を認めています。
結局、遺産は相続人らが相続する財産ですから、相続人全員の合意があれば、一度決めた分割方法を見直し、再度遺産分割協議を行うことができます。
(3) 遺産分割協議において決められた代償金の支払い
1. 遺産分割協議条項の不履行
遺産分割協議は有効に成立したものの、事後的に一部の相続人がその協議条項を履行しない場合があります。
例えば、ある相続人が特定の遺産を相続するかわりに、 他の相続人に対して金銭を支払うという分割方法(代償分割)を決定したものの、その相続人が金銭を支払わないという場合が考えられます。
契約の場合には、債務不履行解除という制度が存在し、不履行を受けた相手側が契約解除を行って、その契約を無かった状態に戻すということが認められています。
遺産分割においても、通常の契約における債務不履行と同様に、代償金の不払いを理由に遺産分割協議を解除できるかについて問題となります。
2. 最高裁平成元年2月9日判決
最高裁は、遺産分割は、その性質上協議の成立とともに終了し、 その後は協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと判示しました。
すなわち、遺産分割による法律関係の早期安定を重要視して、たとえ分割条項の不履行があった場合でも、遺産分割のやり直しは認められません。
不履行を受けた相続人が、不履行を行った相続人に対して、民事訴訟でその履行ないし損害賠償を求めることとなります。
以上の点から、遺産分割において、代償分割のように一部の相続人に債務負担させる条項を設ける場合には、後の不履行による遺産分割の解除が認められないことを念頭においた上で、同時履行条項を設けたり、相当の担保の提供を求めたりするのがよいでしょう。
(4) 遺産でない財産を遺産として遺産分割した場合
1. 他人の財産混入の遺産分割
相続開始後、遺産の調査を行った上で、相続人間で遺産分割協議を行います。
調査の結果、財産の名義が被相続人であったために遺産分割の時点では、この財産を遺産として遺産分割を行ったものの、後にそれが被相続人の財産ではなかったという事態が生じることがあります。
この場合、非遺産に関する遺産分割条項はどうなるか、他の遺産分割条項に影響を及ぼすかという問題が生じます。
2. 非遺産に関する遺産分割条項
他人物を勝手に分割しても、そのような遺産分割に効力はなく、非遺産に関する分割条項は無効となります。
たとえ、遺産分割審判を経ていた場合でも、遺産分割審判は遺産分割の前提問題について既判力を有しないとされているため、遺産分割審判も非遺産の部分については効力を失います。
3. 他の遺産分割条項への影響
遺産分割条項で非遺産の取得者と定められた者は、当初予定された財産を相続できなかったため、この不足分について他の相続人に対して権利主張していくこととなります。
各共同相続人は他の共同相続人に対して、売主と同様の担保責任を負うと規定されているため、これに基づいた処理がなされます。
すなわち、非遺産が遺産分割において重要な位置づけを占めており、非遺産以外の分割条項を維持することが遺産分割の趣旨を没却するような場合には、遺産分割そのものの解除が認められます。
そうでない場合は、非遺産により不利益を被った相続人が、他の相続人に対して金銭での損害賠償を求めるということになるものと思われます。
(5) 裁判で遺産分割の効力を争う場合
1. 遺産分割不存在確認、無効確認訴訟
遺産分割協議がされていないのに、遺産分割協議書が偽造されているような場合には、遺産分割協議不存在確認訴訟を提起することになります。
遺産分割協議に無効原因(当事者の逸脱、意思無能力、錯誤無効等)がある場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提起することになります。
2. 遺産確認訴訟
家庭裁判所で遺産分割の審判が下された場合でも、遺産の範囲など前提事項を争いたい場合には、別途民事訴訟を提起して、前提問題の確定を求めることができます(最高裁昭和41年3月2日判決)。
問題となっている財産が被相続人の遺産であることの確認を求める場合は遺産確認訴訟、遺産でなく第三者の財産であることとの確認を求める場合は、その第三者が所有権確認訴訟を提起することになります。